基礎物理、化学
| 項目 | 説明 |
| 単体(物質) | 同じ元素で出来ている、それ以上ほぐせない、O2酸素、H2水素、Fe鉄、S硫黄など |
| 化合物(物質) | 2種類以上の元素で、H2O(水)水素+酸素 CO2(二酸化炭素)炭素+酸素 NaCl(塩化ナトリウム)、C2H5OH(エチルアルコール)元の性質と違う物になる |
| 混合物(物質) | 色々な物質が混じり合っている(科学的に結びついていない)空気(酸素+窒素+二酸化炭素)、海水(塩+水)、ガソリン、灯油などそれを表す化学式が無い |
| 原子(元素) | 原子は元素記号で表す、酸素→O、窒素→N、炭素→C、まとめると 原子<元素<単体 |
| 純物質 | 化学式で表す、酸素O2、水H2O など |
| 物理変化 | 本質は変わらないで、色や形など見た目が変わる(水を冷やすと氷になるなど) |
| 三態変化 | 固体、液体、気体に変わる事を言う |
| 化学変化 | 全く違う性質の物質に変わる変化、酸化、燃焼、分解、中和など(ガソリンが燃えて水と二酸化炭素に変わるなど) |
| 化学変化の種類 | 化合(違う物が結合して新しい物質になる)、酸化(酸素と結合する)、燃焼(発光と発熱とのなう酸化反応)、分解(1つの化合物が2種類以上の物質になる)、重合(分子化合物が複数結合して大きな化合物になる事をいう、中和(酸性とアルカリ性が化学反応してお互いの性質を打ち消しあう) |
| 酸化反応 | 酸素が増える反応、水素や電子も関与する |
| 還元反応 | 酸素が減る反応 |
| 酸化剤 | 相手を酸化させ、自分を還元させる(酸素を失い易く、電子を取り込みやすい) |
| 還元剤 | 相手を還元させ、自分を酸化させる(酸化しやすい) |
| 酸化剤と還元剤 | 混ぜると爆発的な燃焼が起きる(混合危険) |
| 燃焼 | 熱と光をともなう酸化反応をいう |
| 炭素の燃焼 | 完全燃焼すると→二酸化炭素(空気より重い)が出来る、不完全燃焼すると→一酸化炭素とすすが出来る |
| 一酸化炭素 | 人体に有害、燃焼の可燃物である(空気より軽い) |
| 燃えやすい状態 | 発熱量の大きい物、空気との接触面積が大きい物、熱伝導率の小さい物は熱をためて燃えやすい、水分が少ない物も同じ |
| 蒸発燃焼 | 蒸発する可燃性蒸気が空気と混合して燃える(第4類全て該当する)ガソリン、アルコール等 |
| 分解燃焼 | 熱分解して発生する可燃ガスが先に燃焼する物(木材、石炭) |
| 表面燃焼 | 固体の表面で燃焼する物(木炭、コークス) |
| 内部燃焼 | 酸素を含んでいる物質が、含有する酸素で燃焼する(セルロイド等) |
| 爆発 | 発行と発熱に爆音がともなうもの、鉄も粉じんなら爆発します。 |
| 混合危険 | 酸化性物質と還元性物質を合わせると酸化還元反応が起こり爆発 |
| 固体の燃焼形態 | 有炎燃焼(ロウソクの様に炎が見える)ガスが酸素と反応する、無炎燃焼(線香の様に炎が出ない)一酸化炭素が出やすい |
| 液体の燃焼形態 | 気化した蒸気が燃える蒸発燃焼 |
| 気体の燃焼形態 | 予混合燃焼は燃料と酸素が混じった状態で火が付く(ガスコンロ)。拡散燃料は燃料と酸素が少しずつ混じり合う(穏やかでゆらゆら) |
| 化学反応式 | 物質がどう変わるかを化学記号で短く表したもの、例 炭素+酸素→二酸化炭素(C+O2→CO2)左が反応する物→右が出来たもの。原子の種類と数は等しい、質量も等しい、物質1モルの質量は分子量にグラムを付ける |
| 代表的な反応式 | 酸素の発生(2H2O→2H2+O2)水が水素と炭素に分かれる、水の生成(2H2+O2→2H2O)水素を燃やすと水が出来る。 二酸化炭素の生成(C+O2→CO2)、一酸化炭素の生成(2C+O2→2CO)酸素が足りない時。 |
| 物理量の定義(1モル) | 質量は原子量(分子量)で求める |
| 原子量例 | 炭素→12、水素→1、酸素→16 |
| アボガドロの法則 | 同じ温度、圧力、体積の気体には同じ数の分子がある(でも重さは違う) |
| 反応熱 | 燃焼熱(物質が1モル完全燃焼する時の反応熱)、生成熱(単体化合物1モルに生成される時の反応熱)、中和熱(酸と塩基が中和して1モルの水になる時の反応熱)、反応熱の総和は、化学反応の経路に関係しない |
| 熱化学方程式 | 化学反応時に出入りする熱(Q)を書き込んだ方程式をいう(物質が燃える時に熱を出しますそれを表した物を言う) |
| 発熱反応 | Q<0、マイナスのQは、発熱反応 熱をだす(水素と酸素を反応させて水を作る時、熱が出ます) |
| 吸熱反応 | Q>0、プラスのQは,吸熱反応 熱を吸う(氷が水になる時) |
| 固体→液体 液体→固体 | 融解 凝固 |
| 液体→気体 気体→液体 | 気化 液化 |
| 固体→気体 気体→固体 | 昇華(ショウカ) 逆も同じ 昇華 |
| 三態変化 | 氷は熱を吸収して水になる、水蒸気は熱を放出して水になる、同じ温度で状態を変化させる熱をセンネツ(状態が変わる)といい(0度の水と氷)、物体の温度変化に必要な熱をケンネツ(温度が変わる)という |
| 蒸発 | 液体の表面から気化が起きる現象 |
| 沸騰 | 液体の中から気化が起きる現象 |
| 沸点 | 液体の飽和蒸気圧と外圧が等しくなる時の液体温度、加圧すると高くなる(減圧すると低くなる山頂は100度以下で沸騰する) |
| 潮解(チョウカイ) | 固体が空気中の水分を吸収して自から溶ける現象(岩塩) |
| 風解(フウカイ) | 固体の水分が蒸発して粉末になる現象 |
| 溶解 | 物質が液体に溶ける事 |
| 臨界点 | 液体として存在できる限界 |
| 三重点 | 固体、液体、気体どの状態も存在できる環境 |
| 比熱 | 1gの物質を1度上げるのに必要な熱量(比重が大きい程、熱量も必要) |
| 熱量 | 比熱x質量x温度差(熱容量=比熱x質量g) |
| 氷→お湯の場合の計算方法 | 潜熱(溶解熱x質量)+顕熱(比重x質量x温度差)=熱量 |
| 伝導 | 高温から低温に伝わる現象 |
| 対流 | 液体と気体に起きる |
| 放射 | 熱が直接当たった面に伝わる |
| 熱伝導率 | 小さい程、熱をためやすく燃えやすい(鉄>液体>気体) |
| ボイルシャルルの法則(気体の膨張) | 圧力x体積/-273度 |
| ガソリンの膨張計算 | 膨張分=元の体積x耐膨率x温度差 |
| 第4類の蒸気比重は | 全て1以上で空気より重い、(二酸化炭素も重い)一酸化炭素は空気より軽い) |
| 酸性 | 青いリトマス紙→赤になる(水素イオンが発生している状態)Hプラス |
| アルカリ性 | 赤いリトマス紙→青になる(水酸化イオンを発生している状態)OHマイナス |
| イオン化傾向 | 金属が陽イオンになろうとする性質(1番イオンになりやすいのは、カリウム)1番なりにくいのは金(ゴールド) |
| 鉄よりイオン化傾向の大きい金属 | マグネシウム、アルミニウムを繋ぐと防食効果がある |

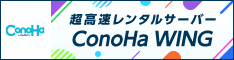







コメント